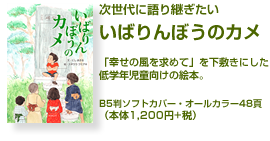コロナ禍の影響で、一年以上延期されていた「鴉根山の狐の像」を設置しました。まだ工事中ですが、こんな様子です。

さて、この狐の紹介です。
明治後期のこと、狐の親子が鴉根山に棲んでいました。ある日、猟に来た亀三郎とばったり、狐は亀三郎に鉄砲で足を撃たれてしまいます。
翌日、足が不自由になった狐が子狐を連れて救済所の近くに来ました。それを見た亀三郎は「人助けに人生を懸けている俺が親子の狐を撃つなんて、なんと軽薄なことを」と、心から後悔、この日を境に猟ををきっぱりと止め、鉄砲を伏見稲荷に献納。そして稲荷のお札を貰い、ここ鴉根に稲荷神社を建立したのです。
亀三郎は狐の親子には棲み処の穴ぐらを提供、狐の親子はこれより長く鴉根の丘で暮らします。狐たちは救済所のシンボルとなり、救済所の人々と仲良く暮らしました。
この狐を祀った稲荷神社は毎年、地元民も一緒にお祭りも行い、それは昭和50年近くまで続いていました。
そうそう、新美南吉も昭和12年の冬にはここ鴉根に住んでいます。当然、鴉根の狐の伝説も知っていて、親友の童謡作家・巽聖歌にそれを話していました。南吉亡き後、巽は半田の岩滑とここ鴉根も訪ねて「これが南吉の言っていた稲荷社なのだ」と書いています。南吉童話の「狐」のモチーフは鴉根山の狐なのです。
さて、その狐の像はようやく設置。この4月24日(土)に関係者を招き、除幕式を挙行します。詳しくは追ってお知らせします。
 Loading...
Loading...